古くから日本でも愛されている梅の木。花は可愛らしくも美しく、見た人の心を癒します。また、梅の花は香りがとても高く、香水などにも使われています。梅の魅力は花だけに留まらず、実は加工して梅干しや果実酒にも用いられ、葉っぱの部分も食用できます。そしてなんと梅には、食用や鑑賞用だけでなく薬となる成分も含まれているのです。この記事は、そんな魅力たくさんの梅を、多様な角度から紹介していきたいと思います。
梅の基本情報
梅は、バラ科サクラ属の落葉高木、またはその果実のことを指します。別名「春告草」「好文木」「木の花」「風待草」と呼ばれています。梅の果実を利用する品種は『実梅』として扱われ、未熟なものは有毒であるものの、梅干しなどに加工して食用とされます。樹木全体と花は古くから鑑賞の対象とされており、日本にも名所が各地にあります。幹がゴツゴツしていることが特徴で、花を見ただけでは桜と区別がつきにくいです。また、梅の枝や樹皮は染色にも使われています。花言葉は『厳しい美しさ、あでやかさ』、原産国は中国です。
昔から愛される美しさ
今でこそ花見の主流は桜ですが、日本で最初の花見の花は梅なのです。お花見は奈良時代の貴族が始めた行事と言われており、当初は中国から伝来した梅の花を観賞するためのものだったようです。そして平安時代に入り、お花見の花が梅から桜へと移り変わっていきました。また、梅は天神様である菅原道真公が生涯愛した花でもあり、菅原家の家紋にもなっています。
香り高き梅の花
梅の花はとても香りが高く、長年多くの人々に愛されてきました。梅は主に、園芸種として三種類に分類することが出来ます。枝が細く、葉はこぶりで原種に近い野梅系(やばいけい)、木質部中心まで赤色で、濃紅色の花も多い緋梅系(ひばいけい)、アンズとの交配種で枝や葉が大ぶりで実を採取することが多い豊後系(ぶんごけい)です。梅の香りは、この分類と花の色に関連していることがわかってきました。
野梅系に属する白から薄桃色の花は、華やかでフルーティな甘い香りが。緋梅系の中でも花色がピンク色から濃紅色の花は、少しスパイシーな甘さのある香りがします。豊後系の梅は香りがないとされており、接ぎ木の台木用・庭木・実梅によく利用されています。また、紅梅より白梅の方が香り高いとされており、実際に紅梅に比べて白梅の持つ香気量の方が多いというデータがあります。
梅の花の効能
梅の花は観賞用だけでなく、薬草として使うことも可能なのです。梅の花にはポリフェノールやクエン酸、ビタミンCなどの成分が含まれています。それらにより、梅には次のような効能があります。
- 消化不良やのどの渇きに効果がある
- お腹の痛みや張りに効果がある
- 痰切れに効果がある
- 梅核気(のどに梅の種が詰まっているような異物感)などに効果がある
- 美肌効果がある
- 疲労回復に効果がある
- 抗酸化作用がある
しかし、注意しなければならない事ももちろんあります。まずは品種です。梅の品種によって花の部分が薬として使用できるかどうかが異なります。また、効能の中に消化不良に効果があると記載しておりますが酸味があるため、胃酸過多や胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の方は控えてください。採取の際の注意点としては、蕾が咲く直前に採り、香りを損なわないよう素早く陰干しをしてください。
上記であげたような効能は、梅の『花』を使った場合です。完熟していない『実』には毒があり、中毒症状を起こしてしまいます。
利用方法
梅の花の効能について話してきましたが、今回は梅の花の利用方法についてです。利用方法は大きく分けて3つ。
- 梅の花茶として飲用する
- 乾燥した花の粉を外用する
- 新鮮な花弁を潰して口内炎や腫物に使う
最後に書いたものは花弁が清潔でなければならないので要注意です。
梅の葉の効能
梅には花以外にも、葉っぱの部分にも薬効があります。梅の葉には抗菌作用や美容成分など、健康に役立つ成分が含まれています。主な効能としては、次のようなものがあります。
- 慢性下痢、月経による不正出血などに効果がある
- 疲労回復や血行促進の効果がある
- ビタミンCによるコラーゲンの生成を促進する効果がある
- ポリフェノールが含まれているため、アンチエイジングとも呼ばれる老化防止の効果
このように、梅の葉には美容に良い効能が多く含まれています。また、こちらは余談ですが梅のその他の効能として、腸内環境を整え、便秘予防、肥満や糖尿病予防、免疫力アップ、抗アレルギー効果など様々な効果が期待されています。その他、食材の腐敗を抑える抗菌作用も持っており、食材の保存性を高める効果もあります。
梅の葉の利用方法
梅の葉は花と同様、梅の葉茶というお茶にして飲用することが出来ます。また、梅の花や果肉、梅干し、米糠、黒糖、酵母菌などを発酵させて作る梅酵素ドリンクなどでも利用することが出来ます。
梅染
梅の花や葉には薬として使用することが出来ますが、枝や樹皮は染色として利用されます。梅染と呼ばれる染色技法で、室町時代から加賀で行われた無地染めの技法です。そしてなんと梅染は、加賀友禅の起源とされているのです。品種は紅梅のものを使い、樹皮や根を煎じた汁で染めたものやその色を指します。赤みのある茶色のものを『赤梅染』、黒ずんだ茶色のものを『黒梅染』といいます。媒染剤にはミョウバン、灰汁、鉄漿(てっしょう)、石灰などが用いられました。
加賀友禅との関係
上記で加賀友禅の起源と記しましたが、そちらについて少し触れていきます。加賀友禅の始まりは、加賀独特の染め技法である「梅染」まで遡ります。17世紀中頃になると、模様染めである「加賀紋」や「兼房染」の技法が確立され、梅染・加賀紋・兼房染を総称して『お国染め』といい、加賀友禅の原点と言われています。そして江戸時代中期に、宮崎友禅斎が絵画調の模様染めを指導したところから、加賀友禅が確立されました。
いかがでしたでしょうか。このように古くから薬として、染色として、癒しとして愛されてきた梅の木。樹齢は長いもので400年を超えるとされ、日本の歴史を見守ってきました。この歴史ある美しい梅の世界の魅力を、記事を通じて少しでも知っていただけたら幸いです。全国各地に存在する梅の名所。ぜひこの機会に、桜だけではなく梅の花も見に行ってみてはいかがでしょうか。

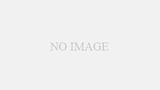
コメント